PR ※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

Googleの持ち株会社であるアルファベットが株式分割(1:20)の計画を出しましたね。アルファベット(クラスC株:議決権なし)の2月3日の終値が2852.84米国ドルなので、株式分割されると単価が140米国ドルくらいになり一般の投資家にも手が出しやすくなります。まだ計画を発表しただけのようですが、一般投資家の買いも入りやすくなるので株価が上がると予想されているみたいですね。高配当株をメインに据えていますが、ちょっと心が揺らいでいます。さて、今回は前フリとは関係のない“食品ロス(フードロス)”に関する記事です。お得に食材を入手する手段として“ふるさと納税”が有名ですが、確定申告が必要だったり、確定申告不要のワンストップ特例というものがあったり、上限額が決まっていたり・・・。地域に寄付できる素晴らしい制度であることは理解しているのですが、情報があふれて何が正しいのかわからず、なかなか取っ付きにくく感じてしまいます。今回ご紹介するサービスは、上限もなく、面倒なアクションもありません!食品ロスに関心のある方、気軽に社会貢献してみたい方はぜひご覧ください。
おすすめのサービス5選
結論から書きますと、おすすめサービスは次の5つです。
- ロスオフ(旧:在庫ロス掲示板)
- KURADASHI(クラダシ)
- junijuni(ジュニジュニ)
- Otameshi(オタメシ)
- ハピタスアウトレット
おすすめする理由は後述します。
ロスオフ(旧:在庫ロス掲示板)

強み・特徴
ロスオフは、在庫を抱えた生産者の方々と消費者をつなぐプラットフォームです。
個人的に思うロスオフの強みは
- 生産者の方を直接応援できる
- 流通コストが削減されるので、お得なお値段で購入できる
- 在庫や廃棄が減るので、食品ロスの削減に貢献できる
- 品揃えが豊富
もっと言ってしまうと、お得に食材が買えるうえに、生産者の方々の応援もできてラッキー!といった感じです。調味料の購入の時に使ってみましたが、感想としては社会貢献している感覚はあんまりないですね。
バーベキューや燻製用の食材として使えそうな肉・魚だけでなく、アルコールやお菓子も取りそろえており、見ているだけでも楽しめます。公式サイトはこちら
KURADASHI(クラダシ)

強み・特徴
KURADASHI(クラダシ)は、食品ロス削減に賛同してくれた企業から協賛価格で提供を受けた商品を扱っています。このため、通常より手頃なお値段で購入可能です。お値段なんと最大97%オフだそうで、すごいですね。また、売上の一部を社会貢献団体に寄付しており、KURADASHIを使うことで手軽に社会貢献できます。なお、一般会員は注文1件ごとに550円の送料(税込)がかかります。公式サイトはこちら
junijuni(ジュニジュニ)

強み・特徴
junijuni(ジュニジュニ)は東京ガスがスポンサーを務めるECサイトです。賞味期限の近い商品や訳あり品を企業から買い取って安く販売しています。食品ロスの削減につながるほか、売上の一部が社会貢献団体に寄付されるため、社会貢献もできます。私は基本的に食品の部分以外チェックしませんが、日用品もあるようです。3,980円以上の注文で送料が無料になります。公式サイトはこちら
Otameshi(オタメシ)

強み・特徴
Otameshi(オタメシ)は、KURADASHIやjunijuniと同様、賞味期限の近い商品や旧パッケージなどの訳あり品をお手頃価格で購入できるECサイトです。食品ロスの削減につながるほか、売上の一部が社会貢献団体に寄付されるため、社会貢献もできます。公式サイトはこちら
ハピタスアウトレット
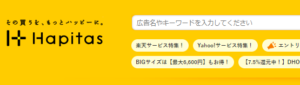
強み・特徴
ハピタスアウトレットは、名前からお察しかもしれませんが、ポイントサイトの一つである『ハピタス』の中にあります。過剰生産やパッケージ変更、賞味期限の近い商品をアウトレット品として購入できます。公式サイトはこちら
まとめ
冒頭に記載したとおりですが、おすすめ5選は次のとおりです。
- ロスオフ(旧:在庫ロス掲示板)
- KURADASHI(クラダシ)
- junijuni(ジュニジュニ)
- Otameshi(オタメシ)
- ハピタスアウトレット
あくまで個人の感覚で書きますが、肉や魚のようないかにも食材っぽいものが欲しかったり、農家さんや漁師さんなど生産者の方を直接応援したい方は『ロスオフ』が一番適しているように感じます。新型コロナウィルスの感染拡大で、飲食店が休業したり、観光地が打撃を受けていますが、そこに食材を提供している生産者の方も打撃を受けていますので、こういったサービスを活用して支援できればと思っています。
【参考】食品ロスについて

食品ロスは令和1年度で年間570トン。一人あたりで計算すると45kg/年。1日の数字にすると一人あたりお茶碗一杯分の食品を廃棄しています。家庭で食品ロスを減らす努力は私たち一人ひとりが取り組むことができます。一方、パッケージ変更や賞味期限が近付いたものなど、まだ食べられるのに廃棄されてしまう事業系の食品ロスについて、一般消費者としての私たちができることはあまりなかったように思います。せいぜい、恵方巻やクリスマスのケーキを予約して買うくらいでしょうか。2020年に感染拡大が始まった新型コロナウィルスの影響を受け、飲食店や観光地で消費されるはずだった食品が行き場をなくしている現状に対して、今回の記事でご紹介したサービスはお得に買い物できるだけでなく、生産者の方のためにも活用していきたいと思いますし、それを広めていくことで、結果として食品ロスの削減につなげていくことができると思っています。ロスが減ると、企業の業績も徐々に上向き、株価の上昇や配当金の増額といった形で投資家に還元されてくると思います。もちろん、今回ご紹介したサービスを提供している企業が上場するなら投資を検討してもよいと思っています。最後、無理やり投資に話をつなげた感は否めませんが、たまにはこんな風に投資を考えてみてもよいのかな、と思います。
おすすめ食品ロスアプリとその選び方!

近年、食品ロス(フードロス)を減らすためにアプリを利用する人が増えています。食品ロスを減らすために適切な量を購入し、食材をできる限り活用することはサステナブルな社会にとってとても大切です。食品ロス削減アプリを利用すると、食品ロスを減らせるだけではなく、お店の利益が増えたり、安く食品が買えたりするなどのメリットがたくさんあります。食品ロス削減アプリの概要、食品ロスアプリを利用するメリット、おすすめアプリについて詳しく解説します。
食品ロス(フードロス)とは

日本では「食品ロス」と「フードロス」は混同され同義で使われることが多いですが、海外での「フードロス(Food Loss)」は、生産・収穫された食品のうち、輸送や製造、加工など消費者に届く前の段階で廃棄になってしまう食べ物のことで、「食品ロス(Food Waste)」は食べ残しや、家庭で捨てられてしまう食べ物を指します。日本国内での食品ロスはFood LossとFood Wasteを合わせたものを指します。日本の最新(令和4年度)の食品ロス量は472万トン、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は236万トン、家庭から発生する家庭系食品ロス量は236万トンとなり徐々に食品ロス量は減少しています。近年食品ロス対策のためにさまざまな取り組みが行われている中のひとつにフードシェアリングという仕組みがあります。余った食材や料理を消費者のニーズとマッチングする機会をつくることで、食品ロスを減らす仕組みです。 提供者側の具体的なメリットとしては食品ロス・廃棄コストの削減、売上増、新規顧客の獲得といった経済的メリット以外にも、SDGsへの貢献、ブランディングなどがあります。また食品ロスを削減していくためには、ご飯を残さず食べるといった個人としての意識・活動はもちろんのこと、お店や自治体との協力も必要です。食品ロス削減アプリと呼ばれるものは主にフードシェアリングアプリです。中でも通販型と店舗訪問型に分かれます。また、レシピアプリや食材管理アプリなども有効に活用することで食品ロスを削減できます。
フードシェアリングアプリ
食品ロスが予想される食品、食材、料理を消費者とマッチングするアプリです。「店舗訪問型」では飲食店などで閉店までに売り切ることが難しく廃棄が発生しそうな場合などにアプリに登録し、直接店舗まで訪問できる消費者がそれを少し安い価格で購入できます。 「通販型」では消費期限が近くなってしまった商品をアプリに登録し、消費者が有料もしくは無料で購入します。
レシピ活用型の食品ロスアプリ
食品ロスアプリとは認識されていないかもしれませんが、食材から検索できるレシピアプリは食品ロス削減の強い味方です。
食材管理型の食品ロスアプリ

食材管理アプリでは家庭にある食材を登録しておくことで、消費期限を把握して期限切れを防いだり、家にあるもので作れるレシピをおすすめしてくれるものもあります。ほかにもwebアプリ「食品ロスダイアリー」では、未使用食品や食べ残しを毎日どれぐらい捨ててしまったか記録につけることができます。
食品ロスアプリの選び方
食品ロスアプリの種類について説明しましたが、様々なフードシェアリングアプリがある中で、それぞれ取り扱う商品の種類や送料・会費の有無、対応エリアなどに違いがあります。ほかにも売上の一部を寄付しているなど、自分が共感できるということも選ぶポイントになります。
・取り扱い商品のジャンル
食料品のなかでも加工食品、生鮮食品、お酒、スイーツ、調味料また日用品や家電製品、化粧品など食品以外のものを取り扱っていることもあります。
・割引率
アプリによって割引率も様々です。無料の場合もあります。
・対応エリア
店舗訪問型では自分が住む地域で利用可能かどうか必ず確認しましょう。
・会費など
アプリにより利用料や手数料等その他の費用の有無があります。
その他、アプリ内にフードバンクの情報や、食品のレビューやアプリ内SNSコミュニティ機能があるものもあります。
まとめ
食品ロスを減らすためのアプリはいくつか存在し、利用料や手数料の有無、受取方法の違いや展開しているエリアなどそれぞれに特色があります。あなたのライフスタイルに最適なアプリを選ぶ助けになるよう、各アプリの違いを把握し、あなたの生活スタイルやニーズに合わせて、最適な食品ロスアプリを見つけてみましょう。
食品ロス削減のためのヒント
1.必要な分を購入する
買い物前に自宅にある食材を確認するなどして、必要な時に必要な量を購入することで無駄を減らすことに繋がります。
2.期限表示を確認する
最近ではスーパーなどの小売店でも「てまえどり」などと表示されていますが、すぐ使う予定の食材は棚の手間に置かれている賞味期限の近いものを買うと店舗での廃棄の削減になります。
3.訳あり品を購入する
消費期限が近い商品や規格外商品などは安く売られていることもあり、食品ロスの削減とお金の節約にもなります。
4.食品を正しく保管する
食品は適切な方法で保存し、廃棄することなく使い切りましょう。冷蔵庫や冷凍庫、保管庫なども整理することで賞味期限切れを見落としづらくなります。
フードシェアリングに参加する

フードシェアリングにはフードバンクやフードドライブなどもあります。
フードバンクとは、企業や農家などの生産者から寄付された食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を、福祉施設や、貧困世帯へ無料で提供する活動です。フードドライブは、家庭で余った食品を持ち寄り、フードバンクや福祉施設・団体、子ども食堂などに寄付する活動を指します。
フードドライブは、受け入れている団体などを調べて、個人でも行うことができます。
食品ロスアプリの将来展望
政府や自治体、企業、学校など様々なプレーヤーが、フードロス削減に向けて取組を行っています。 日本でのフードロス削減アプリの利用経験率は8.4%とまだまだ低いですが、新しいサービスや現状のシステムが拡充されていくことで利用者が増えていくと考えられます。
技術の進化と新機能の予測と社会的な普及の可能性

すでにAIを活用したアプリも登場していますが、今後さらに消費者にあった食品ロスの仕組みが広がると思われます。
2019年には日本でも食品ロス削減推進法が施行されました。食品ロス削減推進法は「国、地方公共団体、事業者、消費者の多様な主体」が対象であり、事業者だけでなく国民全体で連携し取り組むことを目指した法律です。
このようななかで食品ロスアプリはますます一般に浸透していくと考えられます。
食品ロスアプリのインパクト

食品ロスアプリの「Kuradashi」では、フードロス削減の効果として、フードロス削減量25,333t CO2削減量67,159t 経済効果 123億2,580万円【2024年9月時点】となっています。また、売り上げからの寄付の支援額は1億円を超えています。 食品を扱う上で、どうしても出てしまう規格外の食品や、賞味期限切れによる廃棄も、このような仕組みによって、生産者が個人でも食品ロス削減につなげることができ、また消費者も食の現状を知ることで、誰からどのようなものを買うのか、自分自身で選択するための情報を与えてくれます。
食品ロス削減によるエコロジーへの貢献

食品ロスに直接関わる食糧問題、食品の輸送時に排出されるCO2、廃棄の際の焼却処理時に発生する温室効果ガスによる地球温暖化への影響、廃棄食料の焼却灰による埋め立ての問題、バーチャルウォーター(食料を生産する際に使用した水のこと)の問題など食品ロスの削減は様々な問題に良い影響を与えます。

